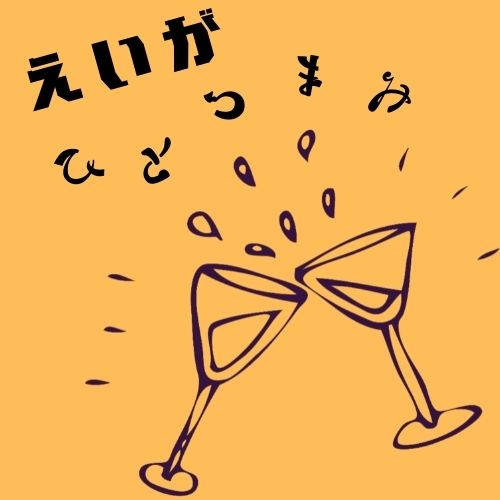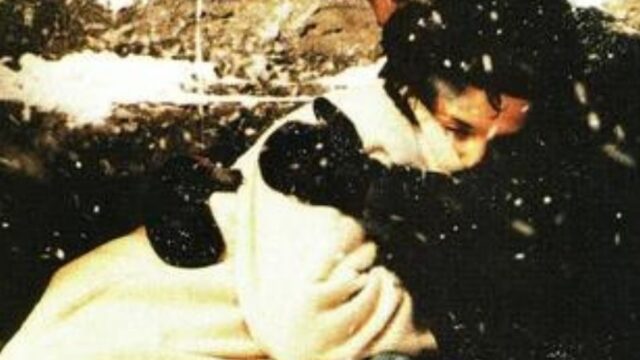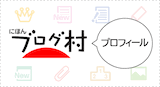画像引用:©1994, 2008 Block 2 Pictures Inc. All Rights Reserved.
こんにちは!ころっぷです!!
今日の映画は【恋する惑星】です。
1994年に制作されたウォン・カーワァイ監督の代表作。
中国に返還される直前の香港の空気感。
時代を経ても古びれない斬新な映像表現。
エネルギッシュかつファンタジックな浮遊感。
若き才能達の即興演技と即興演出が、
映画の魔法を堪能させてくれる作品です!!
この映画はこんな人におススメ!!
●とにかくお洒落な映画が観たいという人
●アジアの雑然とした雰囲気が好きな人
●都市生活者の孤独と浮遊感を味わいたい人
●時代を象徴する映画の革命を目撃したい人
| タイトル | 恋する惑星 |
| 製作国 | 香港 |
| 公開日 | 1995年7月15日(日本公開) |
| 上映時間 | 100分 |
| 監督 | ウォン・カーウァイ |
| 出演 | トニー・レオン、フェイ・ウォン、 ブリジット・リン、金城武 |
映画の初期衝動を感じたい時に観る映画
今作が日本で公開されたのは1995年。
わたくしころっぷ少年が15歳の時でした。
当時映画に興味を持ち始めた頃で、
映画雑誌の表紙はとにかくウォン・カーウァイ作品か、
クエンティン・タランティーノ作品かという様な時代でした。
サブカルチャーというものが市民権を得始めた頃でもあり、
それまでのメジャーシーンとは一線を画す通好みの作品が持て囃されていました。
この【恋する惑星】もミニシアターから火が点いての記録的なロングランヒット。
映画雑誌だけでは無くファッション誌が特集を組む程、
お洒落な雰囲気が人気を集めていました。
時を経て今改めてこの映画を観てみると、
如何にこの作品が斬新で衝撃的であったかを再認識させられます。
60年代のフランスで起こったヌーヴェルヴァーグを彷彿とさせる様な、
激しいカメラワークと矢継ぎ早のカット割り。
強烈な陰影や色彩の撮影にセンスの良いサウンドトラック。
当時まだ無名に近かった若手俳優達の自然体の演技が印象的でした。
同じ1994年に制作されていた、
オールスター大作【楽園の瑕】の撮影に息詰まっていたウォン・カーウァイ監督が、
そのフラストレーションをぶつける様に即興演出で完成させた今作品。
クリエイターとしての初期衝動に満ちたヒリヒリ感と、
返還直前の香港の混沌とが見事にフィルムに刻み込まれています。
正に成るべくして成った運命的な映画と言えるのでは無いでしょうか。
浮遊する夜の若者達

画像引用:©1994, 2008 Block 2 Pictures Inc. All Rights Reserved.
物語は二部構成になっています。
一話目は恋人に去られた刑事のモウ(金城武)と、
金髪のウィッグを付けた麻薬ディーラー(ブリジット・リン)の出会いを描いた話。
そして二話目はこちらも恋人と別れた警察官633号(トニー・レオン)と、
食堂の店員フェイ(フェイ・ウォン)との出会いの話。
共に香港の重慶大廈(チョンキン・マンション)を舞台に、
都会の雑踏の中で不器用に生きる若者達の等身大の姿を描いています。
まるで光に集まる虫の様に、孤独を胸に肩を寄せ合う男女の姿。
活き活きとした彼等のエネルギッシュな表情が、
夜の街にネオンの灯りの様に浮かび上がります。
時代の大転換期にあった香港には、
どこか目的を失った様な閉塞感が漂っています。
気怠く生温い風に包まれる様な空気感。
じっとりと汗を肌に這わせ、見えない未来に目を凝らす。
ウォン・カーウァイのカメラはそんな90年代末期の香港を、
見事に真空パック保存しています。
どこか場当たり的で、冗談の様でありながら、必死でもある。
そんな若者達の姿が時を経ても色褪せずに普遍的である事が驚きです。
1960年公開のジャン・リュック・ゴダール監督作品【勝手にしやがれ】の、
ジャン=ポール・ベルモンドとジーン・セバーグのカップルが
今観ても古びれないのと一緒で、
カーウァイ監督の描く登場人物達も時の洗礼を受けても色褪せません。
それは彼等の内面から滲み出てくる個性を掬い上げる様な、
繊細かつ大胆な演出が即興的に成されたからに他ならないのです。
最高の組み合わせ

今日のおつまみは【ヒラマサの刺身】です。
いよいよ春本番の暖かい季節になってきて、
花見も待ち遠しいですが、
旬にはまだ少し早いヒラマサの刺身がスーパーで美味しそうだったので、
堪らず日本酒のアテに食卓に上りました。
やっぱりこういう時日本人で良かったなぁなんて思います。
香港映画を観ながら余り情緒も無いのですが、
美味しいものは美味しいのです。
ここでは無いどこかへ

画像引用:©1994, 2008 Block 2 Pictures Inc. All Rights Reserved.
今作のテーマは一体何だったのでしょうか?
一見無軌道に見える若者達の言わばその場のノリの様な会話と恋愛。
互いの心の隙間を品評し合う様なライトな関係性。
そこに流れる時間の感覚と時代の温度感が、
彼等の未来をどこか窮屈に暗示している様な気がします。
何時の世にも誰の元にも困難は存在しますが、
食うに困る様な、命に関わる様な危機でも無い。
無理に同調するよりも個性を重んじる様な風潮でもあり、
孤独であっても不幸では無い。
そんな宙ぶらりんの都会生活者のリアリティが、
ウォン・カーウァイの描きたい人間達の姿だったのかも知れません。
それは今現在も大きく変わってはいません。
インターネットやコンプライアンスは日々進化していても、
本質的に人間の営みに違いは無いのです。
人は現状に満足する事は無く、
常にここでは無いどこか。
こんなでは無い自分。
もっと素晴らしい筈の未来を夢見て右往左往するのです。
過去の失恋を引き摺っていながら、
新しい出会いにも自分の気持ちに素直になれない登場人物達。
そこに我々観客は強く共感し、既視感だったり理想だったりを重ねるのです。
映画の初期衝動を感じたい時に観る映画。
この作品で世界的な評価を集めたウォン・カーウァイ監督は、
1997年の【ブエノスアイレス】や2000年の【花様年華】などで
更に世界的な評価を高めていきました。
アジアを代表する巨匠となった彼の、
即興演出の革新的な効果が初めて発揮されたのが今作なのです。
映画という多様な文化に於けるささやかな奇跡とも言える作品です。
いつ観ても一瞬で90年代のあの頃の空気感が蘇ります。
まるでタイムカプセルの様に、
たまに掘り出して中身を眺めたくなる様な映画であると個人的には思っています。