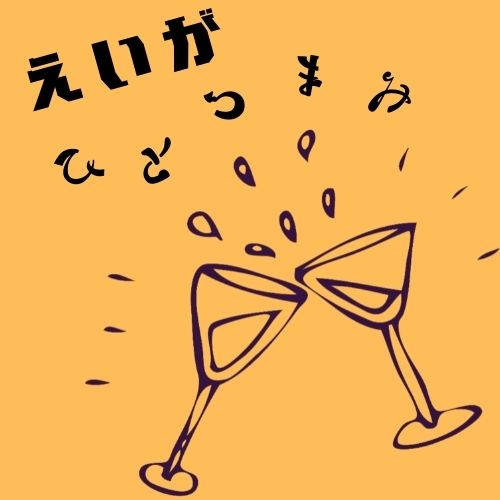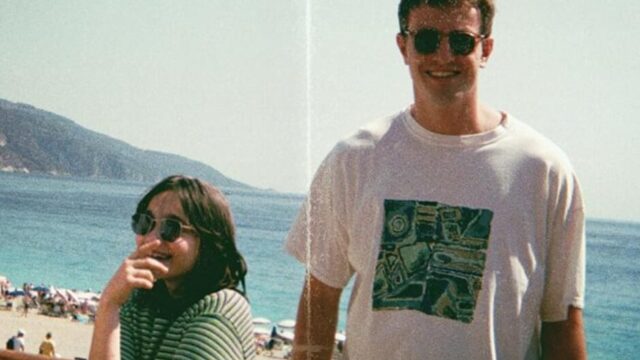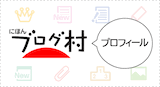画像引用:©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
こんにちは!ころっぷです!!
今日の映画【国宝】です。
100年に一度の映画と巷で騒がれる、
2025年最大の話題作。
3時間弱という長尺にも関わらず、
一寸の弛みの無い緊迫感と圧倒的な映像美。
知られざる歌舞伎の世界にどっぷりと沼れる、
正に奇跡の傑作と呼ぶに相応しい作品です!
この映画はこんな人におススメ!!
●日本の伝統芸能の世界に興味がある人
●兎に角美しい映像を目に焼き付けたい人
●芸の道の厳しさを知りたい人
●互いを高め合う友情を目撃したい人
| タイトル | 国宝 |
| 製作国 | 日本 |
| 公開日 | 2025年6月6日(日本公開) |
| 上映時間 | 175分 |
| 監督 | 李相日 |
| 出演 | 吉沢亮、横浜流星、高畑充希、森七菜、 寺島しのぶ、田中泯、渡辺謙 |
美の極みを目撃したい時に観る映画
映画館の暗闇の中で対峙する3時間弱の梨園の世界。
夢と現を彷徨う様に、
「美」と「芸」の呪いに憑りつかれ、
悪魔と契約し頂点に昇り詰める一人の歌舞伎役者を描いた大河ドラマです。
膨大な時間の稽古によって歌舞伎の所作を身に付けた、
主演の吉沢亮と横浜流星の演技に対する熱量。
【アデル、ブルーは熱い色】などで知られるフランスの撮影監督、
ソファニ・エル・ファニによる圧倒的な映像美。
監督は2006年の【フラガール】や
2016年の【怒り】などで高い評価を得ている李相日。
原作の吉田修一とは三度目のタッグとなる李監督は、
名家に生まれた宿命の子と、
類稀な才能を持って生まれた不遇の子との
因縁と友情の物語を情感たっぷりに演出しました。
一流のキャストとスタッフを集結させ、
伝統芸能の世界を丹念に描いた今作は、
観た者が人に勧めずにはおれない強烈な口コミの力によって、
興行収入100億の大台を突破する勢いの大ヒットとなっています。
歌舞伎の女形を演じる主演の二人の美しさと、
実力派の俳優達の重厚なアンサンブル。
長尺もあっと言う間に感じさせる様な濃密な時間。
「美」というもののある意味での恐ろしさを感じながら、
人間の深い業と芸の道の厳しさを描く。
400年にも及ぶ歌舞伎の歴史の重みと、
それを背負う者達の生き様に迫るドラマ性。
正に全日本人必見の美のエンターテイメントがこれでもかと眼前に繰り広げられる幸福。
今作を見ずして2025年の映画を語る事はまず不可能でしょう。
芸の道に絡め取られる二人の人生

画像引用:©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
物語は任侠の家に生まれ落ちた主人公の喜久雄が、
父親を亡くし上方歌舞伎の名門に見受けされる所から幕を開けていきます。
その家には名跡を継ぐ跡取りの俊介がいて、
二人は終生のライバルとして切磋琢磨し互いに役者として成長していきます。
名門の血筋に生まれ将来を約束された俊介と、
その才能と努力で芸を磨きのし上がっていく喜久雄。
二人は厳しい修行を共に耐える内に深い友情を育み、
怖いもの知らずの若さと勢いで、
次第に歌舞伎界のホープとして世間の注目と期待を集める存在となっていくのです。
最初にこの物語の肝となるのは「血」か「才能」かという二者択一の勝敗。
喜久雄の才能に名跡の跡取りである俊介が圧倒されていく展開に、
結局「歌舞伎」という芸能はどちらを選ぶのかという図式で
二人を描いていく様に見えます。
しかし今作はただ単に二人の立場を対立させ、
そのぶつかり合いでドラマを盛り上げようとはしません。
共に歌舞伎の400年の歴史の重さを理解し、
狭い世界で究極の「美」を追求する者同士として、
唯一自分の孤独を理解し得る存在として、
そして何より苦楽を共にする同志として魂で繋がり合っていくのです。
やがて喜久雄の才能に打ちのめされ姿を消した俊介も、
芸の道を諦める事無く本物の役者になる為に泥を吸ってドサ回りの身で這いつくばる。
その覚悟は「歌舞伎」という特殊な世界が持つ光に魅せられてしまった者の宿命の様。
この作品は「血」か「才能」なのかというテーマが重要なのでは無く、
「芸」の呪いに懸かってしまった二人の若者の執念に喘ぐ姿を通して、
人が一生の内に何を成し得る事が出来るのか。
その最たる姿を持って力強い人間の業を描いたドラマ作品なのです。
おつまみの国宝

今日のおつまみは【ジャージャー麺】です。
ソースと麺は市販のセットですが、
自家製のチャーシューを乗せ枝豆を散らしました。
これは夏にピッタリのおつまみの国宝です。
冷たい麺がどうしても食べたくなる季節ですが、
これはピリ辛のソースと共にスタミナも付くので、
大満足の一皿になりました。
人生の終わりの瞬間に

画像引用:©吉田修一/朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会
劇中いくつかの歌舞伎の演目が舞台で演じられますが、
そもそも男性が女性の役を演じる「女形」という形式も、
知らねば中々異様で不思議な文化だと思いますよね。
歌舞伎の始まりは実は出雲の阿国という女性が男装して踊った事が始まりだそうです。
今と正反対なのですが、風紀の乱れを理由に江戸幕府が女性が演じるのを禁じた為、
その風習が今日まで残っているという事なのです。
この性的な虚が一種歌舞伎の神秘性を象徴しているとも言えますが、
この【国宝】の主人公が「女形」であるという事も実に象徴的であると言えます。
舞台俳優という職業は他人を演じる事が生業ですが、
性も越え時代も越え、世襲という仕来たりも越えた喜久雄が、
次第に自分の人生の虚実からも逸脱した様に精神を病んでいく様は、
役者という職業の業に絡め取られた悲劇であると言えます。
そうとしか生きる術の無かった彼は、周りの好奇の目や嫉妬心に晒され、
ただ己の芸を磨く事でしか生きる道を見出す事が出来なかった。
それ故に後ろ盾を無くし足元が崩れるとどこまでも堕ちてしまい、
現実の世界での覚束ない足元に絶望してしまうのです。
しかしそんな彼を救うのも芸の道。
かつて袂を分かった名跡の御曹司との再タッグが、
彼の役者としての才能を蘇らせ人間国宝となるまで駆け上がらせるのです。
常に彼を支え見守ってきた先達や親友を既に亡くし、
年老いた喜久雄が人間国宝となっても更に望み求めていた景色とは何だったのか?
悪魔を契約し、芸事以外の全てを捨て修羅の道を歩んだ男の最後の望み。
それはかつて子供時代に自分の目の前で凶弾に倒れたヤクザの父親の死に様の景色。
舞台上で何度も繰り返し描かれた雪景色のイメージは、
喜久雄の幼少時のトラウマであり原体験。
舞台の向こう側を初めて垣間見た興奮と運命だったのでは無いでしょうか。
渾身の「鷺娘」を演じ終えた喜久雄は、
まるでその命を燃え尽くした様な恍惚とした表情で、
誰も居ない劇場の天井を見上げ呟きます。
彼はそこに嘗て彼を導いてくれた先達を見、
400年の歌舞伎の歴史を見、
もしかしたら今と違っていたかも知れない、
自分のもう一つの人生を見ていたのかも知れません。
それは全てをやり遂げた男の安堵と解放の微笑みでした。
あのラストシーンに至るまでの3時間弱の積み重ねが、
私達観客と共に壮大なカタルシスへと浄化していく様が、
劇場体験の興奮と相まって絶大な感動を誘ってくれました。
美の極みを目撃したい時に観る映画。
日本映画界の総力を結して紡がれる圧倒的な大河ドラマ。
これを見ずして日本映画は語れない。
そう思わせてくれる作品に久し振りに出会う事が出来て、
映画ファンとしてこれ以上ない幸せを感じさせて頂きました。